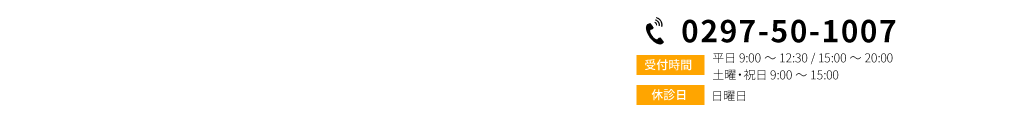月別アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年10月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年5月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年2月
- 2022年1月
カテゴリ一覧
- お知らせ (49)
- スポーツ障害 (33)
- その他の症状 (33)
- 上肢のお悩み(首・肩・腕・手) (22)
- 下肢のお悩み(ふともも、膝、足) (23)
- 交通事故治療 (17)
- 体幹のお悩み(背中・胸・腰・お尻) (12)
顔のたるみについて:症状と原因、ケア方法

顔のたるみは、加齢とともに気になりやすいお悩みのひとつです。フェイスラインの崩れやほうれい線の深まり、目元・口元のたるみは、実年齢よりも老けた印象を与えてしまいます。しかし、適切なケアを行うことで、たるみを防ぎ、若々しい表情を保つことが可能です。
守谷市にある「トレーナーステーション整骨院」では、顔のたるみに対する施術を通じて、多くの患者様のお悩みを解決してきました。特にラジオ波マッサージを活用した施術は、肌の引き締めやリフトアップに大きな効果をもたらします。
ここでは、顔のたるみの主な原因や種類、セルフケア方法、そして当院での施術について詳しくご紹介します。
顔のたるみの原因と種類
顔のたるみは、さまざまな要因によって引き起こされます。その原因を理解し、適切な対策を講じることが大切です。
1. 皮膚の弾力低下(コラーゲン・エラスチンの減少)
肌のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンは、加齢とともに減少します。その結果、皮膚が支えを失い、たるみが生じます。
2. 表情筋の衰え
顔の筋肉(表情筋)は、肌を内側から支える役割を持っています。しかし、加齢や表情の乏しさ、長時間のスマホ・パソコン使用によって筋力が低下すると、頬や口元、顎周りがたるんでしまいます。
3. むくみ・血行不良
血流やリンパの流れが悪くなると、老廃物が排出されにくくなり、顔のむくみやたるみにつながります。特にフェイスラインのたるみは、むくみが慢性化することで悪化しやすくなります。
4. 生活習慣の乱れ
睡眠不足や栄養バランスの乱れ、ストレスの蓄積なども顔のたるみの原因になります。特に糖分や脂質の摂りすぎは、肌の老化を早める要因になります。
5. 重力による皮膚の下垂
年齢とともに皮膚や脂肪が重力に負け、下方向に引っ張られることでたるみが発生します。特に頬やフェイスライン、目元のたるみは顔全体の印象を大きく左右します。
顔のたるみを防ぐセルフケア
1. 表情筋トレーニング
- 口を大きく開けて「あ・い・う・え・お」と発声
- 頬を膨らませたりすぼめたりして、口周りの筋肉を刺激
- 上を向いて「いー」と言いながら口角を引き上げる
2. 保湿とスキンケアの強化
- コラーゲンやヒアルロン酸配合の保湿クリームを使用
- 顔をマッサージしながらスキンケアを行い、血行を促進
- 日焼け止めを使用し、紫外線ダメージを防ぐ
3. 姿勢を意識する
- デスクワーク中は背筋を伸ばす
- スマホを見る際は目線の高さを意識
- 枕の高さを適切に調整し、首に負担をかけない
守谷市「トレーナーステーション整骨院」でのたるみ改善ケア
当院では、顔のたるみに対する専門的な施術を提供し、内側からの改善を目指します。
1. ラジオ波マッサージによるリフトアップ
ラジオ波マッサージは、肌の深部まで熱を届け、血行促進やコラーゲンの生成をサポートする施術です。
✅ 皮膚の深部を温め、血流を促進
✅ リンパの流れを良くし、老廃物を排出
✅ コラーゲンの生成を促し、ハリや弾力をアップ
✅ 即効性があり、施術後すぐに引き締まりを実感できる
特に、フェイスラインのたるみや頬のもたつき、むくみにお悩みの方におすすめです。温熱効果により深部から肌の代謝を高めることで、たるみだけでなく小顔効果も期待できます。
2. 骨格矯正と筋肉の調整
顔のたるみは、姿勢や噛み合わせのズレが原因となっていることもあります。当院では、骨格矯正を行い、顔や首の歪みを整えることで、フェイスラインのたるみを改善します。
3. 美容鍼による血行促進
当院では、美容鍼も取り入れています。極細の鍼を使って顔のツボを刺激し、血行を促進することで肌のターンオーバーを活性化します。美容鍼とラジオ波マッサージを組み合わせることで、さらに高いリフトアップ効果が期待できます。
トレーナーステーション整骨院が選ばれる理由
守谷市の「トレーナーステーション整骨院」では、顔のたるみに悩む患者様に寄り添い、最適な施術を提供しています。
- ラジオ波マッサージによる高い即効性
- 美容鍼との組み合わせでより高いリフトアップ効果
- 骨格矯正による根本的な改善
- 一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイド施術
フェイスラインのたるみが気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
顔のたるみは、適切なケアを行うことで改善が可能です。守谷市にある「トレーナーステーション整骨院」では、ラジオ波マッサージを中心に、美容鍼や骨格矯正を組み合わせた多角的な施術で、リフトアップをサポートします。
たるみのない、若々しく引き締まったフェイスラインを目指しませんか?
お気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。
目の下のクマ

目の下のクマは、疲れた印象を与えたり、実際の年齢よりも老けて見られる原因となるお悩みのひとつです。守谷市にある「トレーナーステーション整骨院」では、目元のクマに対する施術を通じて、多くの患者様のお悩みを解消してきました。原因や種類を正しく理解し、それに合ったケアを行うことで、目元の印象を大きく改善することが可能です。ここでは、クマの主な原因や種類、当院でのケア方法についてご紹介します。
目の下のクマの種類と原因
目の下のクマには、以下のような種類があります。それぞれ異なる原因を持つため、適切な対処が必要です。
- 青クマ
青クマは、目の下に青や紫色の影が見えるのが特徴です。主な原因は目元の血行不良で、睡眠不足やストレス、目の酷使が血流の悪化を招く要因となります。血液中の酸素不足が皮膚を通して透けて見えることで、青や紫色に見えるのです。 - 茶クマ
茶クマは、目の下に茶色の色素沈着が現れるタイプです。紫外線の影響や、アレルギーによるかゆみで目をこする習慣、また皮膚の炎症が原因となり、メラニン色素が蓄積します。摩擦や紫外線対策を怠ることで悪化しやすい特徴があります。 - 黒クマ
黒クマは、目元の皮膚のたるみによる影が原因です。肌のハリや弾力が低下し、目の下の凹凸が強調されることで発生します。加齢による皮膚の老化や、長時間のデスクワークによる姿勢の悪化が関係しています。
クマを改善するためのセルフケア
目の下のクマを改善するには、原因に合ったセルフケアを取り入れることが大切です。
- 青クマのケア
血行不良が原因の青クマには、目元を温めるホットタオルや温湿布が効果的です。また、全身の血流を促進するために適度な運動を取り入れたり、ストレッチを行うこともおすすめです。 - 茶クマのケア
茶クマを改善するには、紫外線対策が欠かせません。UVカット効果のあるアイクリームや日焼け止めを使用し、目元の保護を心がけましょう。また、目元をこする習慣をやめ、クレンジングやスキンケア時には優しく扱うようにしましょう。 - 黒クマのケア
黒クマを防ぐためには、目元のハリを保つことが重要です。目元専用の保湿クリームや美容液で保湿を徹底するほか、表情筋を鍛えるための簡単なエクササイズもおすすめです。睡眠時の姿勢を工夫し、むくみを防ぐことも効果的です。
守谷市「トレーナーステーション整骨院」でのケア方法
当院では、目の下のクマに対する専門的な施術を提供しています。一人ひとりの症状や原因に合わせたアプローチで、目元のお悩みを根本から改善していきます。
- 鍼灸による血行促進
青クマの原因である血行不良には、鍼灸施術が効果的です。目元や顔のツボを刺激することで血液の流れを改善し、クマを軽減します。さらに、全身の巡りを整えることで、体全体の調子を整えます。 - ラジオ波マッサージでの肌改善
茶クマや黒クマにお悩みの方には、ラジオ波マッサージが有効です。ラジオ波によって肌の深部を温め、血行促進や代謝向上をサポートします。これにより、茶クマの色素沈着の軽減や、黒クマの原因となる肌のたるみ改善が期待できます。また、コラーゲンの生成を促し、肌にハリを取り戻す効果もあります。 - 骨格矯正と筋肉の緊張緩和
黒クマの原因であるたるみや姿勢の悪さには、顔や首の骨格矯正、筋肉調整が有効です。首や肩の凝りを緩め、正しい姿勢を保つことで目元のたるみを改善し、若々しい印象を取り戻します。
トレーナーステーション整骨院が選ばれる理由
守谷市の「トレーナーステーション整骨院」では、目元のクマに悩む患者様に寄り添った施術を行っています。患者様一人ひとりの症状やライフスタイルを丁寧にヒアリングし、最適なケアをご提案いたします。当院の施術は即効性だけでなく、根本的な改善を目指したアプローチが特長です。クマのお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
目の下のクマは、原因によって適切なケア方法が異なります。守谷市の「トレーナーステーション整骨院」では、鍼灸やラジオ波マッサージ、骨格矯正など多角的なアプローチで、目元のお悩みを改善します。疲れた印象や老けた印象を解消し、自信のある明るい目元を手に入れませんか?お気軽にご相談ください。専門のスタッフが、親身になってお手伝いさせていただきます。
寝違えとは?
寝違えは、朝起きたときに首や背中に痛みやこわばりを感じる状態を指します。これは、寝ている間に首や背中の筋肉が過度に屈曲したり、不自然な姿勢を維持し続けたりすることが原因となります。常に起こるものではありませんが、首周辺の筋肉に負荷がかかるストレス状態や床域環境が大きく影響するとされています。

寝違えの原因
1. 不適切な床域環境
- 床上での現象は、枕が首の形状に合わない場合や、床板やマットの硬さが不適切な場合に起こることがあります。首が無理な姿勢になると、筋肉に過度な負荷がかかります。
2. 布団の使用方法
- 寝ているときに布団が体を半分くらいしか覆いていない場合や、完全に覆いていない場合、体が寒さを感じて筋肉が緊張することがあります。
3. 労働や運動の負荷
- 日常の労働や運動で筋肉に負荷がかかり、ある部分の筋肉が緊張したままになっていると、寝ている間に痛みやこわばりを感じやすくなります。
4. 運動不足による体力低下
- 体力が低下している場合、筋肉や構造が疲れやすくなり、寝違えの危険性が高まります。
寝違えの症状
寝違えの症状は人によって異なりますが、主に以下のような状態が見られます。
- 首や背中の痛み:労働に支障が出ることもあります。
- 首を動かすときの痛み:得に左右に首を伸ばす動作で痛みが高まります。
- 背中の筋肉のこり感:緊張感が続く場合があります。
- 可動域制限:首周辺の動きが制限されたように感じることがあります。
予防方法
寝違えを防ぐための注意点を下記します。
- ストレッチ
- 不適切な枕の交換
- 床域の温度管理
- 日常的な運動体操の進行
守谷市にあるトレーナーステーション整骨院でのサポート
トレーナーステーション整骨院では、寝違えの症状に応じた施術を行っています。
- 鍼灸治療:痛みを緩和し、血流を改善することで回復を促進します。
- 手技療法:筋肉や関節の緊張を緩め、首の可動域を広げます。
- 運動指導:自宅でできる簡単なストレッチやエクササイズを提案します。
寝違えでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。症状に合わせた適切な施術で健康をサポートいたします。
寝違えについてのQ&A
Q1. 寝違えはなぜ起こるのですか?
A: 寝違えは、睡眠中の不自然な姿勢や枕の高さが原因で、首や肩の筋肉に過剰な負担がかかることで発生します。また、日頃の疲労や筋肉の硬さが影響することもあります。特に、長時間同じ姿勢で寝ていると血流が悪くなり、筋肉や靭帯が緊張しやすくなるため、朝起きたときに痛みや動きの制限を感じることがあります。
Q2. 寝違えたときの対処法は何ですか?
A: 寝違えたときは、無理に首を動かさず、まずは安静にすることが大切です。痛みを感じる部分に冷湿布を貼って炎症を抑えるのが効果的です。また、温めるのは痛みが軽減した後に行うようにしましょう。ただし、強く揉んだりストレッチをするのは逆効果になる場合があるため注意してください。当院では、適切な施術を通じて、寝違えによる痛みや緊張を速やかに改
スマホ頭痛とは
近年、スマートフォンの普及により、「スマホ頭痛」と呼ばれる症状が増加しています。スマホ頭痛とは、スマートフォンを長時間使用することによって引き起こされる頭痛のことを指します。この頭痛は、首や肩の筋肉の緊張や姿勢の悪化が原因で発生し、多くの現代人が悩まされています。

スマホ頭痛の原因
スマホ頭痛の主な原因としては、以下のような要素が挙げられます:
- 長時間の前かがみ姿勢
スマートフォンを見る際、多くの人は無意識に首を前に突き出す姿勢になります。この状態が続くと、首や肩周りの筋肉に負担がかかり、筋肉の緊張が頭痛を引き起こします。 - 眼精疲労
小さな画面を長時間見つめることで目が疲れ、眼精疲労が起こります。眼精疲労が進行すると、頭痛や肩こりを伴うことがあります。 - 血行不良
長時間同じ姿勢でいると、血流が悪くなり、酸素や栄養が十分に筋肉や脳に行き渡らなくなります。その結果、頭痛が発生することがあります。 - ストレスや睡眠不足
スマートフォンの過剰使用による夜更かしやブルーライトの影響で睡眠の質が低下し、ストレスが溜まることで頭痛を引き起こす場合もあります。
スマホ頭痛の症状
スマホ頭痛の主な症状は以下の通りです:
- 頭の前面や側頭部の鈍い痛み
- 首や肩のこり・痛み
- 目の奥の疲労感や違和感
- 集中力の低下やイライラ感
- めまいや吐き気を伴う場合も
これらの症状が続く場合、日常生活に支障をきたすだけでなく、慢性的な頭痛へと発展する可能性があります。
スマホ頭痛の予防方法
スマホ頭痛を予防するためには、以下のポイントを意識することが大切です:
- 正しい姿勢を保つ
スマートフォンを見る際は、画面を目の高さに近づけ、首を前に傾けすぎないようにしましょう。 - 適度な休憩を取る
1時間に1回は画面から目を離し、首や肩を軽く動かして血行を促進します。 - 目を休める
20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先を見る「20-20-20ルール」を取り入れると、眼精疲労を軽減できます。 - ストレッチを取り入れる
首や肩周りの筋肉をほぐすストレッチを日常的に行い、筋肉の緊張を和らげます。 - ブルーライト対策
スマートフォンの設定でブルーライトを軽減するモードを使用したり、ブルーライトカット眼鏡を活用することも有効です。 - 十分な睡眠を確保する
良質な睡眠をとることで、身体全体の回復力を高め、ストレスを軽減します。
守谷市にあるトレーナーステーション整骨院でのサポート
トレーナーステーション整骨院では、スマホ頭痛の改善に向けた以下の施術を行っています:
- 鍼灸治療
ツボを刺激することで、筋肉の緊張を和らげ、血行を改善します。 - 整体・骨格調整
スマホ頭痛の原因となる姿勢の歪みを整え、身体のバランスを改善します。 - リラクゼーションマッサージ
首や肩の筋肉をほぐし、リラックス効果を高めます。 - 生活習慣のアドバイス
正しい姿勢やストレッチ方法、日常生活での注意点をお伝えし、再発を防ぎます。
おわりに
スマホ頭痛は現代社会において誰にでも起こりうる問題です。しかし、適切な対策や治療を行うことで、改善が期待できます。よつば鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状に合わせた丁寧な施術を行い、健康な身体作りをサポートいたします。スマホ頭痛にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
スマホ頭痛についてのQ&A
Q1. スマホ頭痛ってどんな症状ですか?
A: スマホ頭痛は、長時間スマートフォンを使用することで首や肩に負担がかかり、頭痛として現れる症状です。スマホを見る際、頭が前に傾き、首や肩の筋肉に過度な緊張が生じることが原因です。また、画面の光や集中による目の疲れも頭痛を引き起こす要因になります。頭が重く感じたり、こめかみや後頭部がズキズキと痛む場合は、スマホ頭痛の可能性があります。
Q2. スマホ頭痛を予防・改善する方法はありますか?
A: スマホ頭痛を予防するには、以下のポイントを意識しましょう:
- 正しい姿勢を保つ
スマホを目の高さに合わせ、背中をまっすぐにして首や肩への負担を軽減しましょう。 - 休憩をとる
30分ごとにスマホを置いて、首や肩を軽く動かしたりストレッチを行うことをおすすめします。 - 画面の明るさを調整する
スマホの画面を適度な明るさに設定し、目の負担を減らしましょう。
股関節痛とは
股関節痛とは、股関節周辺に痛みや違和感を感じる症状の総称です。この症状は、年齢や生活習慣、運動習慣などによって引き起こされ、放置すると日常生活に支障をきたすことがあります。特に高齢者や運動を頻繁に行う方に多く見られる症状です。

股関節痛の原因
股関節痛の原因はさまざまですが、主に以下のようなものがあります:
- 加齢による変化
加齢とともに関節の軟骨がすり減り、関節炎や変形性股関節症が発生することがあります。 - 運動や姿勢の問題
過度な運動や誤った姿勢が原因で、股関節に過剰な負担がかかり、痛みを引き起こします。 - ケガや外傷
転倒や事故による骨折や捻挫が股関節の痛みの原因となることがあります。 - 炎症や疾患
股関節周辺の筋肉や腱に炎症が生じることや、関節内の疾患が痛みを引き起こす場合があります。
股関節痛の症状
股関節痛の症状は、痛みの程度や原因によって異なります。主な症状は以下の通りです:
- 歩行時の痛みや違和感
- 股関節を動かした際の痛み
- 安静時でも感じる鈍い痛み
- 股関節周辺の腫れやこわばり
股関節痛の予防と対策
股関節痛を予防するためには、以下のような対策が効果的です:
- 正しい姿勢の維持
日常生活での姿勢を見直し、股関節に無理な負担をかけないようにしましょう。 - 適度な運動
股関節周りの筋力を強化する軽い運動やストレッチを取り入れることで、股関節の安定性を高めます。 - 体重管理
適切な体重を維持することで、股関節への負担を軽減できます。 - 定期的なケア
違和感を感じた際は早めに専門家に相談し、適切なケアを受けることが重要です。
守谷市にあるトレーナーステーション整骨院でのサポート
当院では、股関節痛の改善に向けた以下の施術を提供しています:
- 整体・骨格調整
股関節周辺の歪みを整え、負担を軽減します。 - 鍼灸治療
痛みを和らげるためのツボを刺激し、血流を促進します。 - 筋肉のリラクゼーション
マッサージやストレッチを通じて筋肉を緩め、動きを改善します。 - 生活習慣の指導
股関節に優しい生活習慣や運動方法を提案します。
おわりに
股関節痛は放置すると悪化し、生活の質に影響を及ぼす可能性があります。よつば鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状に合わせた丁寧な施術を心がけています。股関節痛にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
股関節痛についてのQ&A
Q1. 股関節痛はどのような症状が特徴的ですか?
股関節痛の症状として、股関節周辺の痛みや違和感、歩行時の痛み、脚を動かした際の可動域の制限が挙げられます。特に、立ち上がりや階段の昇降時に痛みを感じることが多く、症状が進行すると日常生活に支障をきたす場合があります。
Q2. 股関節痛の原因にはどのようなものがありますか?
股関節痛の原因として、加齢による関節の変形(変形性股関節症)、スポーツや過度な運動による過負荷、姿勢の歪み、筋力の低下、股関節周辺の筋肉や腱の炎症が挙げられます。また、特定の疾患や先天的な異常が原因となる場合もあります。
むくみとは
むくみとは、体内の水分が皮膚の下や組織間に過剰に溜まることで、腫れや違和感を感じる状態を指します。むくみは、主に脚や顔、手に現れやすいですが、全身に発生する場合もあります。一時的なむくみであれば問題ありませんが、慢性的なむくみは健康上の問題を示すサインである場合があります。

むくみの原因
むくみの原因は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです:
- 血行不良
長時間同じ姿勢でいることや運動不足により、血液やリンパの流れが滞ることでむくみが生じます。 - 塩分の過剰摂取
塩分を多く含む食事を摂ると体内に水分が溜まりやすくなり、むくみを引き起こします。 - ホルモンバランスの変化
女性の場合、月経前や妊娠中、更年期などホルモンバランスの変化によりむくみが生じることがあります。 - 疲労やストレス
身体が疲れていると、リンパの流れが悪くなり、余分な水分が排出されにくくなります。 - 疾患の影響
心臓や腎臓、肝臓の病気が原因でむくみが発生する場合もあります。この場合は早めの診察が必要です。
むくみの症状
むくみの主な症状は以下の通りです:
- 腫れぼったい感覚
- 肌を押すとへこみが残る(指圧痕)
- 重だるさや疲労感
- 靴や指輪がきつく感じる
- 筋肉のこわばりや痛みを伴うことも
むくみの予防と対策
むくみを予防・改善するためには、以下の方法が効果的です:
- 適度な運動
ウォーキングや軽いストレッチで血行を促進し、むくみを防ぎます。 - 塩分を控える食事
塩分を控えたバランスの良い食事を心がけることで、水分の溜まりを予防できます。 - 水分補給
適度な水分を摂取することで、体内の水分バランスを整えます。 - リンパマッサージ
リンパの流れを良くするために、むくみが気になる部分を優しくマッサージします。 - 適切な休息
足を高くして寝ることで、血液やリンパ液が循環しやすくなります。
守谷市にあるトレーナーステーション整骨院でのサポート
当院では、むくみの改善に向けた以下の施術を提供しています:
- リンパマッサージ
リンパの流れを促進し、体内の余分な水分を排出します。 - 鍼灸治療
ツボを刺激して血行やリンパの流れを改善します。 - 骨格調整
姿勢の歪みを整え、むくみの原因を根本から解消します。 - 生活習慣のアドバイス
食事や運動、セルフケアの方法をお伝えし、むくみの再発を予防します。
おわりに
むくみは放置すると慢性化し、生活の質を低下させる原因となることがあります。よつば鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状に合わせた最適な施術を行っています。むくみでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
Q1. むくみは何が原因で起こるのでしょうか?
むくみの主な原因は、血行不良やリンパの流れの滞り、塩分の摂り過ぎ、ホルモンバランスの変化、疲労やストレスなどです。また、長時間同じ姿勢でいることや運動不足もむくみを悪化させる要因となります。疾患が原因の場合もあるため、慢性的なむくみが気になる場合は医師に相談することをお勧めします。
Q2. むくみを解消するために自宅でできる対策はありますか?
はい、以下の方法を試してみてください:
- 足を心臓より高い位置に上げて休む
- 塩分を控えた食事を心がける
- ウォーキングやストレッチで血行を良くする
- むくみが気になる部分を優しくマッサージする
- 十分な水分を摂り、体内の水分バランスを整える
むくみがひどい場合や、セルフケアで改善が見られない場合は、専門的な施術を受けることをお勧めします。
五十肩とは?
五十肩(肩関節周囲炎)は、肩関節の周囲に炎症が起きることで、肩の動きが制限される状態を指します。特に40代から60代の中高年層に多く見られるため、「五十肩」という名前が付けられています。症状は肩の痛みや可動域の制限が特徴で、日常生活に大きな影響を与えることがあります。

五十肩の原因
五十肩の正確な原因は完全には解明されていませんが、以下のような要因が関係していると考えられています。
- 加齢による変化:肩関節やその周囲の組織が老化により硬くなり、炎症を引き起こしやすくなります。
- 過度な使用:肩を酷使することが炎症の引き金になる場合があります。
- 血行不良:肩周辺の血流が悪くなることで、炎症や痛みが起きやすくなります。
- 基礎疾患:糖尿病や甲状腺疾患などの病気を持つ人は、五十肩になりやすい傾向があります。
五十肩の症状
五十肩の症状は進行段階によって異なりますが、以下の3つの時期に分けられます。
1. 急性期(痛みの時期)
- 肩の動きに関係なく、じっとしていても痛みを感じる。
- 夜間に痛みが強くなり、睡眠を妨げることがある。
2. 慢性期(硬縮の時期)
- 肩の痛みは徐々に軽減するが、肩の可動域が大幅に制限される。
- 洋服を着る、髪をとかすといった日常動作が困難になる。
3. 回復期
- 痛みがほぼ消え、肩の動きが徐々に改善していく。
- 回復には数ヶ月から1年以上かかる場合がある。
五十肩の診断
五十肩の診断は、主に症状の聞き取りと身体の動作検査によって行われます。必要に応じて以下の検査が追加されることもあります。
- X線検査:骨の異常がないか確認。
- MRI:肩周辺の組織や腱の状態を詳しく調べる。
- 超音波検査:炎症の有無や腱の損傷を確認。
五十肩の治療方法
五十肩の治療は、痛みの軽減と肩の可動域の回復を目指して行われます。
保存療法
- 薬物療法:消炎鎮痛剤や筋弛緩剤を使用して痛みを和らげます。
- 理学療法:温熱療法や電気刺激療法で炎症を抑え、血流を促進します。
- 運動療法:ストレッチや筋力トレーニングを行い、肩の柔軟性を取り戻します。
注射療法
痛みが強い場合、ステロイド注射やヒアルロン酸注射が行われることがあります。
手術療法
保存療法で改善が見られない場合、肩関節鏡を使用した手術が検討されることもあります。ただし、五十肩は多くの場合、保存療法で回復が見込めます。
五十肩の予防方法
五十肩を予防するためには、日常生活で肩の柔軟性を保つことが重要です。
- 定期的なストレッチ:肩関節を動かすストレッチを習慣化する。
- 適度な運動:肩周りの筋肉を鍛えることで関節への負担を軽減。
- 正しい姿勢:悪い姿勢を改善し、肩周辺の血流を促進する。
- 寒さ対策:肩を冷やさないように心掛ける。
守谷市にあるトレーナーステーション整骨院でのサポート
トレーナーステーション整骨院では、五十肩の症状に応じた施術を行っています。
- 鍼灸治療:痛みを緩和し、血流を改善することで回復を促進します。
- 手技療法:筋肉や関節の緊張を緩め、肩の可動域を広げます。
- 運動指導:自宅でできる簡単なストレッチやエクササイズを提案します。
五十肩でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。症状に合わせた適切な施術で、肩の健康をサポートいたします。
五十肩についてのQ&A
Q1. 五十肩は何が原因で発生しますか?
A. 五十肩は、加齢による組織の硬化や炎症、肩の過度な使用、血行不良などが主な原因とされています。また、糖尿病や甲状腺疾患といった基礎疾患を持つ方は発症リスクが高まります。
Q2. 五十肩は放置しても治りますか?
A. 放置しても自然に治る場合もありますが、治るまでに数年かかることがあります。放置することで症状が悪化するリスクもあるため、早めに適切な治療を受けることをお勧めします。
Q3. 五十肩の痛みを和らげる簡単な方法はありますか?
A. 痛みを和らげるためには、温めることや軽いストレッチが効果的です。また、痛みが強い場合は無理をせず、専門家に相談することが重要です。
ばね指とは?
ばね指(弾発指)は、指の腱や腱鞘(けんしょう)に炎症が起こり、指の動きが制限される状態を指します。この状態になると、指を曲げたり伸ばしたりする際に引っかかりや痛みを感じ、時には指が固まったように動かなくなることがあります。この引っかかりの動作が「ばね」のように感じられることから、「ばね指」と呼ばれています。

ばね指の原因
ばね指の主な原因は、指の腱とその周りを覆う腱鞘の間に摩擦や炎症が生じることです。具体的には以下のような要因が挙げられます。
- 手や指の過度な使用:特に手作業や重いものを持つ動作を繰り返す職業や趣味が影響することがあります。
- 加齢:加齢に伴い腱や腱鞘の柔軟性が低下し、炎症が起こりやすくなります。
- 性別:女性の方が男性よりも発症しやすい傾向があります。
- 健康状態:糖尿病やリウマチなどの疾患を持つ方は、ばね指になりやすいと言われています。
ばね指の症状
ばね指の症状は進行具合によって異なりますが、以下のようなものが一般的です。
- 指の違和感や痛み:特に指を曲げたり伸ばしたりする際に、痛みやこわばりを感じることがあります。
- 引っかかり感:指の動きに「カクッ」とした引っかかりが生じます。
- 指のロック:指が曲がったまま、または伸びたままで動かなくなることがあります。
- 腫れや圧痛:腱鞘の部分が腫れたり、触れると痛みを感じることがあります。
ばね指の診断
ばね指は、医師や専門家による診察で診断されます。診察では、以下の点が確認されます:
- 症状のヒアリング
- 指の動きや引っかかりの有無
- 腫れや圧痛の部位
必要に応じて、超音波検査やMRIが行われることもあります。
ばね指の治療方法
ばね指の治療は、症状の軽減を目的として行われます。以下のような方法があります:
保存療法
- 安静:手や指を休ませることで炎症を抑えます。
- サポーターやスプリントの使用:指の動きを制限し、腱と腱鞘の摩擦を減らします。
- 薬物療法:痛みや炎症を抑えるための消炎鎮痛剤やステロイド注射が用いられることがあります。
手術療法
保存療法で症状が改善しない場合には、手術が検討されることがあります。手術では、腱鞘を切開して腱の動きを改善します。手術は比較的短時間で行われ、多くの場合、術後すぐに日常生活に復帰できます。
ばね指の予防方法
ばね指を予防するためには、以下のような工夫が役立ちます:
- 手や指を酷使しすぎないように注意する。
- 作業の合間にストレッチを行い、筋肉や腱の緊張をほぐす。
- 適切な道具や作業環境を整えることで、負担を軽減する。
- 糖尿病などの基礎疾患を適切に管理する。
守谷市にあるトレーナーステーション整骨院でのサポート
トレーナーステーション整骨院では、ばね指の症状に対して以下のような施術を行っています:
- 鍼灸治療:炎症を抑え、血流を改善することで症状の軽減を図ります。
- 手技療法:腱や筋肉の柔軟性を高め、指の動きをスムーズにします。
- テーピング:指の負担を軽減し、日常生活をサポートします。
ばね指の症状でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。症状に応じた適切な施術で、快適な生活を取り戻すお手伝いをいたします。
ばね指についてのQ&A
Q1. ばね指は放置しても自然に治りますか?
A. 軽度のばね指であれば、安静にすることで症状が改善する場合もあります。しかし、放置すると症状が悪化し、指の動きがさらに制限されることがあります。早期の適切な対処が大切です。
Q2. ばね指になりやすい指はありますか?
A. ばね指はどの指にも発生する可能性がありますが、特に親指、中指、薬指に起こりやすい傾向があります。これらの指は日常生活で使用頻度が高いため、負担がかかりやすいとされています。
Q3. 手術後に再発することはありますか?
A. 手術によって症状が改善されるケースが多いですが、稀に再発することがあります。特に手や指を過度に使用し続ける場合や、糖尿病などの基礎疾患がある場合は注意が必要です。
倦怠感

こんな症状はありませんか?
- 体がだるい
- 寝てもだるさがとれない
- やる気が起こらない
- 行動するよりじっとしていることが増えた
- 慢性的に疲労感がある
- 今まで活動的にできていたことができなくなっている
全身がだるい、精神的にだるいなど、これまでになかっただるい症状が出ているなら、ぜひ一度守谷市のトレーナーステーション整骨院までご相談ください。
だるさがあるということは、体が弱っている証拠です。
自然に治ると信じて放置してはいけません。
疲れたら体がだるくなるのは当たり前に思うかもしれませんが、休んでもとれないだるさは、普通のだるさとはいえません。倦怠感といって、体が弱っているサインです。
それだけ疲労が慢性化しているということで、その疲労感は神経や内臓にも悪影響を及ぼします。メンテナンスが必要です。
ただの疲労で片付けず、トレーナーステーション整骨院で相談をしましょう。だるさのなかった以前の状態へ戻していきます。
倦怠感の原因とは?

現代は、倦怠感が出やすい時代ともいえます。倦怠感が出る原因は一つだけではありません。
現代社会は、パソコンやスマホによってかなり便利になりました。
自転車や車、バイクなど便利な移動手段もあり、動かなくても用事が済むようになっています。
動くことが減ると、「歪み」という骨格バランスが崩れる症状が出てきます。私たちの体は、動くことによってバランスを保とうとする力を持っています。
しかし、じっとして動かないことが多いと、体がゆがんでしまいます。
体がゆがむと筋肉が緊張して硬くなります。
この緊張が倦怠感を引き起こします。
緊張している状態は、自律神経のうち交感神経が優勢に働いている状態です。交感神経がずっと活発になっていれば、神経細胞内に細胞を損傷する活性酸素が増えてきます。
この活性酸素によって神経が酸化すると老廃物が発生し、老廃物が増えると疲労因子が出てきます。
疲労因子は脳に伝わります。だから人は疲労を感じます。疲れを感じることはよくありますが、問題は疲労感が長く続くことです。
その結果、全身だるいといった倦怠感が発生し、ひどいと日常に支障が出てきます。
倦怠感の施術とは

守谷市のトレーナーステーション整骨院では、全身の倦怠感を改善するために身体の歪みを改善していきます。
手技やパーソナルトレーニングで、お身体の歪みをキレイに整えていきます。
倦怠感を予防するには
次のことを避けることで、倦怠感を予防できるでしょう。
- 睡眠不足
- お酒
- ヘビースモーカー
- 偏食
- 運動不足
- ストレス
トレーナーステーション整骨院では、全身の血行を改善し、ゆがみも整えていきます。全身に倦怠感を感じにくい体を取り戻せるようサポートします。再発予防にも取り組みます。
こんにちは!
トレーナーステーション整骨院です!
【寒さによる首肩腰の痛みに注意⚠】
急に冬らしく寒さが辛くなってきました。
寒いと人の筋肉は硬くなり、血流が悪くなることで痛みや動きの悪さから疲れやすくなったりします。
まずは体を冷やさないことと、軽くでもいいので体温が上がるような運動を行うことが重要になるのですが、筋肉が硬いと怪我の元になってしまうので、身体の筋肉をほぐして、痛みや辛さをとるようにすることが大事です。
筋肉が硬くなると血行が悪くなり、高血圧になったり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高くなりますので
思い当たる方は早めのケアをしましょう。
当院では、体の筋肉をほぐし、ラジオ波やハイボルトで身体の姿勢や状態を整えます。
場合によっては自律神経も緊張していて辛くなることもあるので、緊張やストレスをとり除く治療を行っていきます。
ぜひ当院にご相談ください。
お待ちしております!